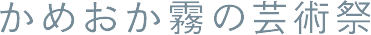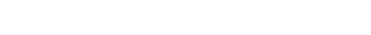開催
終了
南丹高校のSDGs ✖️かめおか霧の芸術祭 〜WEB展覧会〜
- かめおか霧の芸術祭
- 開かれたアトリエ
かめおか霧の芸術祭では、南丹高校3年生の生徒さんが「総合的な探究の時間」で、問題意識を持ち、その解決のために、人に会い、現場に立って経験したことを、ウェブでの展覧会として、発表します。
【チーム1 : 有機農家さんに行ってみた】
私たちのチームは、亀岡市内の若手有機農家さんの「めぐる農園」に行って、実際に有機野菜を収穫したり、農家のご夫婦のお話を聞いたりしました。
チームの中には、おばあちゃんの畑を時々手伝っているメンバーもいるので、元々農業に親しみがあり、いつになるかはわからないけれど、いつかは自分も農業をする日が来るのかな・・・という思いがあります。と同時に、若い人が農業をしているイメージがあまりなく、実際に畑にいるのは年配の方ばかりのように感じています。「農業=年配の人の仕事」という印象があって、まずはそれを変えていかなくては!という思いが、活動のきっかけです。

おばあちゃんが育てた野菜が食卓にのぼる日もあり、畑は自分たちにとって身近で、大切な存在です。そこで私たちは、もっと若者が農業に目を向けてくれるよう、農業がかっこいい仕事であることを伝えたいと思いく、SNSで農家の情報を発信したり、農業の魅力を伝えるポスターを作ろうと考え、「めぐる農園」に話を聞きに行きました。
「めぐる農園」は、ご夫婦(+犬 レティ)で営んでおられる、亀岡市内の有機農家さんです。
ご主人の溝口 竜也さんは、宮城県で漁師をし、その後世界一周の船旅に出られました。その船旅で出会われたのが、現在一緒に畑を営まれている奥様です。
船旅を終え、「自然の中で働きたい」という思いを持ち、2022年6月に、亀岡で農業を始められました。

最初は、虫による被害や亀岡という土地の寒暖差、霧の影響などで、難しいこともあったそうですが、現在は少量多品目で、大根やじゃがいもをはじめ、さまざまな京野菜もを育てておられます。
自分たちも、畑で野菜を収穫させていただきました!

コストを下げるために、大量に生産するのではなく、生態系への影響を最小限に抑えるため、農薬や化学肥料を使わず、有機肥料(油粕や鶏糞・バーク堆肥など)を使って栽培しているという、こだわりがかっこいいと思いました。

「めぐる農園」のお二人は、農業を始める前に、他の農園で経験を積み、勉強されたそうです。
自分たちも高校を卒業しそれぞれの道に進みますが、そこで得る知識や経験を様々な場面で活かせるよう、学び続けたいと思いました。
【チーム2 : コンポストを作ってみた】
まず、「地球にやさしいことってなんだろう」と考えた時に、「ごみ問題」だと思いました。
そして、「環境にやさしくゴミを減らすことができるものはなんだろう」と思い、日常に取り入れることができるコンポストを作ることにしました。
ものを大切にすることはできるけど、食材で食べられない部分はどうしても捨てることになってしまうので、それを活用できないかな、と思ったところで、「土に返す」というとてもシンプルなことに改めて気がついたことが、コンポスト作りのきっかけです。
そこで、「くらしごとLabo」さんに連絡し、「キエーロ」というコンポストの作り方を教えていただきました。

用意するものは、黒土、プランター、ネジ、木の板、プランターに被せる透明の蓋です。
プランターの中に土を入れますが、その土の中の微生物を活性化させるため、日光が必要だし、温度管理も大事です。あまり寒いと微生物は元気がなくなってしまいます。

プランターと蓋の間に木の板を挟むことで、通気性を良くしておきます。
そうしないと微生物が呼吸できなくなり、ガスが溜まってしまいます。
ネジを打ち込んで、木と透明の蓋を固定します。
最後に黒土を入れて、さらに生ゴミを入れて、一回だけ水をかけました。

先生が自宅から持って来られた生ゴミを100円ショップで買ったチョッパーで細かく砕いて使用しました。昆布やバナナの皮、にんじん、卵の殻、玉ねぎの皮などがありました。
ほぼ全部分解されたのですが・・・なぜだか玉ねぎの皮だけ、2ヶ月経っても残っていました・・・。
なんでだろう・・・という話になって、もしかしたら、玉ねぎの皮には農薬がついていて、そのせいで微生物が分解することができないのではないか、あるいは、水分が少ないからではないか、時間が経てば分解するのではないか等、考えてみましたが、検証まではできませんでした。

コンポストを作って、そこでしっかり生ゴミを分解しているのを見た時、
「地球にやさしいものができた!」って思いました。
ゴミを燃やしてしまったら二酸化炭素が出てしまうけれど、燃やすのではことなく分解するのがコンポストなので、地球の温暖化対策にもなるし、いいことがたくさんあると感じました。
令和5年度文化庁文化芸術創造拠点形成事業